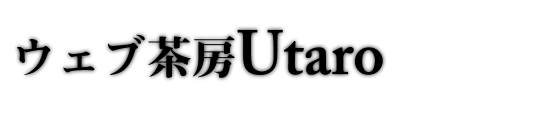![]()
1992年7月2日、専門学校の研修旅行という名目で、沖縄へ、4泊5日の旅をすることになった。
東京はわりと晴れていた。羽田を出発するのは12時45分発の全日空85便。
衣類を存分に詰め込んだバッグを持ちながら、浜松町から始発のモノレールに乗ると、隣に20代後半くらいの、挙動不審の男性がいるのに気づいた。
私は、直感的に身の危険を感じた。しばらくして、その男が訳のわからぬことを言い始めた。
「あーあ、アルプスに帰りたいなあ」
私は最初、その男は誰かと会話をしているのかと思ったのだが、辺りには付添人らしき人物はいなかった。男は独り言を発していたのだ。
「あーあ、もう疲れちゃったよ。ボロボロだよ」
そんなことを、羽田に到着するまで男は発し続けた。私はだんだんと緊張してきてしまったのだが、その男の言うアルプスに何があるのか、少しばかり興味をもったのも確かである。そしてその男はこれからどこへ行こうというのか。男が同じ85便の沖縄行きの飛行機に搭乗して、爆弾を抱えて自殺を図ることを空想したが、思わず嘲笑しそうになった。私がその時考えたことは、実にその程度であった。
初めての体験――飛行機に初めて乗る私は、興奮を抑えながら空の旅を楽しんだ。あいにく雲一色であったが、列車や車のドライブとは違った興奮を味わえた。だから那覇へは本当にあっという間に感じられた。
那覇の地に踏み入れる最初の一歩で、この土地の暑さを感じた。それはむさ苦しさではない、愛着のある暑さであり、昔、少年時代に浴びた時の、身体が記憶していた懐かしいそれであった。私は妙に落ち着き払い、飛行機での神経の高ぶりは急激に収まっていった。
那覇空港から国頭郡本部町へ向かうバスの中で、ゆっくりと那覇の町の情景を目に焼き付け、いろいろなことを考えた。それはつまり、子供の時分に戻っていくような逆行感覚であった。
ホテル・ニュータカシに到着したのは、夕方である。しかしまだ、昼間の元気な太陽が空いっぱいに輝いていた。
その日の夜、私は、地元の友人のKの家に電話をかけることにした。だが、沖縄から関東圏まで、電話代がいくらかかるのかちょっと怖かったので、実家に電話をしたという友人に尋ねてみた。
「向こうまでいくらかかった?」
「そうだなぁ。11秒10円ってとこかな」
私は500円分のテレホンカードを持って、電話をかけた。
「はい、もしもし、Kですが…」
結局、K本人は不在だったので、長電話にはならなかったが、新品のテレホンカードには、しっかりと小さい穴が空いてしまった。もったいなかったと思った。
その日、就寝したのは午前3時をまわった頃だった。寝床に就いたのは12時だったのだが、ある同室の3人組が、ラジカセでテープを流していて、そのジェームス・ブラウンの「SEX MACHINE」の曲のせいで、眠れなかったのである。
7月3日:朝9時半にバスで出発して、フルーツランド・万座毛「パイン園」に到着。
ここでは、ハブとマングースの決闘を見物してから、パイン園で土産物を買った。
その後、「国営沖縄記念公園」に寄った。外は非常に日差しが強く暑かった。一見涼しそうな園内の水族館に入っても、大勢の小学生が騒いでいたため、ほとんどビニールハウスの中のような蒸し暑さであった。
帰りに、「東南植物楽園」を見学して、ホテル・エッカへ帰ってきた。
7月4日:午前9時過ぎに守礼門の県立博物館を見学した後、玉泉洞という鍾乳洞に見ることになった。
今回の旅の全貌を、学園祭用のプロモーション・ビデオにするための撮影隊がいて、私の友人もカメラをまわしていた。
玉泉洞内も撮影するため、その友人は重いカメラを持ちながら中へ入った。彼と私は別行動で、撮影がどうなったかはわからなかったが、バスに帰ってきて、彼のカメラにひどく泥が付いているのでびっくりした。
「カメラ落としちゃってね」
そのカメラは壊れていた。私は何か恐ろしいことになるのではないかと不安になった。
その日の最終日程は、太平洋戦争・沖縄戦の爪痕を残した健児の塔~ひめゆりの塔の見学であった。
この場に訪れて、後に私は、ある代表的な沖縄の歌を知ることができた。
「十九の春」
一、私が貴方に 惚れたのは ちょうど 十九の春でした
今更 離縁というならば もとの 十九にしておくれ
二、もとの十九に するならば 庭の枯木を 見てごらん
枯木の花が咲いたなら 十九にするのも やすけれど
三、みすて心が あるならば 早くお知らせ 下さいね
年も若く あるうちに 思い残すな 明日の花
私はこの曲のメロディを知らなかった。が、物悲しい詩である。この詩と、ひめゆり部隊で死んだ女性たちの姿がオーバーラップして、私の心に重くのしかかるのであった。最前線に設けた病棟に勤務し、兵隊の治療看護に努める。だが薬がなくなると、病に伏せる兵の治療はできなくなる。もはや兵を皆殺しにするしか手だてはない。そんな中で、彼女たちも自らの命を絶つ。これまでの看護は一体何だったのか。そうした遣り切れぬ思いで死んでいく者が、私の心をよぎったのである。今はひっそりとひめゆりの塔で鎮魂している彼女たちの思いが、「十九の春」にはある。彼女たちは、訪れた我々すべてに、大切なメッセージを送り続けているのではないか。
その日の夜、帰ってきてから、例の友人とその班の仲間が対立していた。カメラを鍾乳洞で落としてしまい、撮影したテープが全部使えないということで揉めていたのだ。私はその間に入って宥めたが、むき出した感情は双方とも収まる雰囲気にはならなかった。
沖縄といえばやはり海だが、海水浴の予定の7月5日はあいにくの悪天候で、海で遊ぼうという人は多くなかった。朝はまだ晴れていたものの、ムーンビーチに着く頃には曇り空になってしまったのだ。
それでも、せっかくなので、私は無理に海岸に出て泳ぐことにした。この珊瑚礁の海はさすがに美しく、マリンブルーであっても青色のグラデーションが幾層も折り重なっていた。波も荒くなく、海水浴には絶好の海岸に思われた。
海水に浸かると、足場はかなりひどく、珊瑚の残骸で荒れていた。多少冷たかったが、耐えられぬほどでもなかった。
しばらく泳いでいると、沖の方の雲がだんだん黒くなっていき、そのうち監視員の鋭い笛の音がきこえた。その直後、強烈な雨が降ってきた。台風の直撃であった。激しい風と強い雨によって、海水浴は強制的に中止になってしまった。
日に焼ける暇もなく、私は海から退散した。沖縄の海ともこれが最後であった。
その日の午後は、ゲームセンターにあった競馬ゲームで、長い時間を過ごした。
7月6日:沖縄を出発する朝を迎えた。
ホテル生活もけっこう気軽であったし、暑さにも慣れてきた頃だったので、名残惜しい気がした。それでも、東京のような雑踏も、妙に懐かしくなってきた頃でもあった。
那覇空港で軽い食事をして、飛行機に乗り込んだ。私の身体は沖縄を離れ、見馴れた都会の雑踏の中へ潜伏した。
〈了〉
(1992.07)