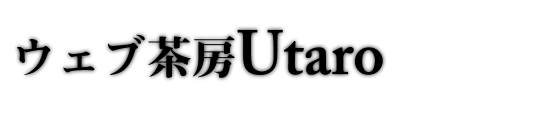![]()
 〈1991年4月2日(火)
〈1991年4月2日(火)
…今日は学校の準備でした。ちょっと遅れてしまいましたが、どうにか間に合いました。でも今日の旅というものは、今までの旅と違うきんちょう感があったと思います。不思議にも初めての今日であるのに、すばらしい出会いに遭遇しました。時間を遅らせた自然は正にこの瞬間のためだったと思います。この出会いはこれからの生活の第一歩であり、相当の安心感を持つことができたのです。彼の故郷ははるばる四国の愛媛にあります。それから埼玉の北千住の近くの町にアパート暮らしを始めたわけです。もちろん故郷から仕送り10万と、ちょっとのかせぎによってこれから毎日生活するわけです。東京についてこれから、どんな生活をするのでしょうか。これまた期待したいと思います。…〉(※〔埼玉の北千住〕は〔東京の北千住〕の誤認)
当時の手書きの個人日記は、青いインクの万年筆で書かれていた。生涯で初めて書き始めた日記であった。筆体は徐々に繊細になり、後半の頁は字数が増え、幾分内容も骨格のあるものと変化した。
「入学式回想録」で既に触れた通り、この1991年4月2日は、入学(入校)の手続きと必要な教材などの手渡し事務が(1号館にて)行われた千代田工科芸術専門学校と私の最初のアプローチであった。とてもよく晴れた1日で、帰途、自宅のある町で電車を降りた私は、この日の出来事を噛みしめるようにして回想し、これほど早く仲間ができたことを嬉しく思いながら、自宅に帰って勢いよく日記に書き綴ったことを思い出す。学校というものがこれほど楽しいものであるかという喜び。それは味わったことのないわくわくした気持ちであり、それまでの学校に対する陰鬱なイメージを一新させる大きな出来事であった。そうしてその後、入学式が4月10日に行われ、本格的に新たな道程を歩むことになる。
ところが――。
愛媛出身の友人の他、いろいろな仲間が繋がっていく中、高校3年から書き続けていたこの一冊の日記は、5月5日の日付で終止符が打たれた。入学から5月5日までの日記には、ほんのごく一部に学校に関する記述があるだけであり、日記の終止符についての具体的な理由は触れられていない。そのごく一部とは、以下のような記述である。
〈…私にとってウェイン・W.ダイアー氏の本を読んで感想を書くという課題は既に無意味に限りなく近いことなのです。感想を述べることはできても、納得することはあっても、新たに見つけることができないのです〉(4月25日付)
ゴールデン・ウイークの連休に伴って芸術課程から課題が出された。ウェイン・W.ダイアー著『もっと大きく、自分の人生!』(知的生きかた文庫)を読んで感想文を提出せよ、という指示だ。
ここに日記の終止符理由の鍵が隠されていると思った。
つまり、何か重大なアクシデント、又は精神的な苦痛を伴う理由によって書くのをやめたのではなく、むしろ逆で、自分自身の心理を探ろうと必死になっていた高校時代の終幕を節目とし、今後はのびのびと生きようという開放的な気分と楽観的な意思が働いたのだろう。それは言わば、センチメンタルな《高校生日記》の終わりを意味していたのだ。であるならば、ウェイン・W.ダイアー氏の著書への半否定も頷ける。
しかもこの頃、中学時代の友人と再会しており、数年ぶりにラジオドラマの自主制作をやろうと意気投合し、後日、実際にそれを実行した。受験勉強の影に潜んでいなければならなかったそうした活動が、今や学業と変わりなく胸を張って堂々とそれができることは、私にとってどれほど開放的であり得たか。さらに付け加えて、この活動が発展深化していき、後々、演劇活動のための小劇団結成へと活発に動いていった。
§
 時代は過ぎ去る。
時代は過ぎ去る。
2011年2月――。鶯谷から台東区根岸へ、3丁目の本藤理髪店の前を通り過ぎ、下谷へと彷徨った。
彷徨ったというより迷い込んだ。
妙なことに、その大きなマンションが建ち並ぶ路地を歩いても、私の心に懐かしいという気持ちが発露しなかったどころか、もっと正直に言えば、自分の歩いている場所がどこだかまるでわからず朦朧としているようだった。
――音ゼミの、あのドラム奏者の青年の顔が浮かぶ。ブラスバンドのチューニングのざわめきが鳴り終わると、一斉に大きな共鳴を響かせて、リズムの整った旋律が路地を突き抜ける。
ズズズズズズ…ババババババ…ブラ~ブラ~ブラ~ブラ~ブラ~ブラ………
画板を引っ提げた青年とその女性らは、煙草を吹かしながら通用口の縁に座り込み、何かを話している。落ち着いた雰囲気をぶち破る青年の威勢のよい言葉が発せられたかと思うと、一同は笑い声に包まれ、またしばらくして落ち着いた雰囲気へと戻る。
授業の合間に私は学校を出て、入谷の交差点付近にある書店で立ち読みをして本を一冊買い込み、再び学校へ戻ってきたところでそんな風景に出合った。それはむしろ忘れるべき他愛のない風景の一場面に過ぎなかった――。
無意識にカメラのシャッターを切ったその場所は、やはり学校の在った路地に違いなかった。しかし、音もなく、ただ午後の黄色い光が路地の空間を斑に射しているだけで、ありきたりな街の路地にしか見えなかった。目印は「文具の島田屋」と「都営下谷一丁目アパート」であるはずが、何故かそれらを視界に留めることができずに、私は浮き足立ったままそこを通り過ぎた。
やがて見えてきたバイク街の一端は、ところどころシャッターが下り、かつての活気は失われているようにも思われた。
だが注意すれば、息づかいはまだあると感じた。健気にも息をしている、と。それらがすべてを失い、真っ白な空間とならないうちに、私は渾然と記録し続けなければならぬと意志を傾けた。そこに居た彼らもまた、私と同じ心持ちであることを信じて止まない。
〈了〉
(2011.02.03)