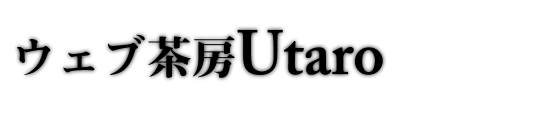![]()
人の心がときめく瞬間を、私は何度も見たし、感じてきた。人の優しさに触れた時、ちょっとしたことで失意から醒めた時…。心の中の雑念であるとか、迷いなどの腫瘍が取れて、まるで青空のように心が澄みきった瞬間――そんな時人間は、円らな瞳を輝かせて無邪気に微笑むのだ。
けれども恐ろしいことに、そうした人間のときめきは、惰性生活の不条理に飲み込まれてしまう場合が多く、純真な感性を錬磨することは極めて困難といえる。そうして無垢であった美しい笑顔も、あの澄みきった心も、肉体から剥がれ落ちていくようにして忘れていく。
ところで、この「忘れる」とは、なんと都合のいい言葉だろう。例えば、日常で氾濫する、
〈あ、忘れてしまいました。すみません〉
という言葉からは、純真さなど微塵も感じられない。裏を返せば、卑劣で傲慢な意思と感じ取れやしないだろうか。
つまり人間には、最初から自分が忘れたことによる他の影響を考えたがらずに、勝手に自己完結させてしまうという悪い習性があるということである。もっとも、人が社会を通じてそうした不条理をばらまきながら生きていることは周知の通りである。
これが芸術の分野になると、「忘れた」という観念に対する嫌悪は、自制しがたいほどの感情に膨れ上がる。ものを作る過程において、何かを作り忘れるということはありえない話ではないか。
むしろ「忘れた」という言葉を吐くこと自体、禁忌である。
芸術家にとって、忘れるという観念は、表現の意義に反した逆行的行為であり、別の言い方をすれば、存在を否定もしくは放棄したと見なしてよいのだ。
芸術家は、自己がときめいた瞬間を逃さない才能を持ち合わせている。どんな局面でであろうとも、それを忘れずに記憶にとどめておこうとする所作こそ、人の表現なのだ。
忘れることに罪悪感をもち、実に些細なことまで書き(描き)留めておこうとする。すなわちそれが、記憶の収集家となっていく。
自分の心の色を読みとって、そして他者の心の色までも読みとる。季節を感じ、時のうつろいを愛し、空気を思う。何よりも大事なのは、対象物との適切な距離関係を決めておくことだ。近すぎず、遠すぎず、微妙な位置に居ること。そうして全体が見えてくる。ときめきもまた、そうした瞬間の一部分にしか過ぎない。
〈了〉
(1997-2000)