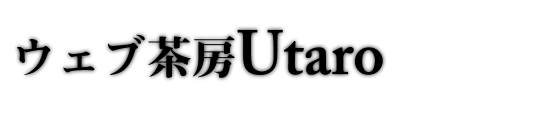![]()
恋人が訪れたのは、駅前の書店であった。学校の帰りのことである。
私ははっきり言って、彼女を待ち伏せしていた。彼女の横に近づくと、その本の表紙のタイトルに指差した。
「私の猫が日本一コンテスト」 彼女は振り向き、私のその指を自分の右手の中に包み込んだ。何とも表現のしようのない温かな手の内だった。私はにっこり微笑んで、彼女を書店の外へ連れ出した。
彼女は振り向き、私のその指を自分の右手の中に包み込んだ。何とも表現のしようのない温かな手の内だった。私はにっこり微笑んで、彼女を書店の外へ連れ出した。
「明日の体育祭、何時だっけ?」
そう質問すると、彼女は無表情で答えた。
「9時半」
その後、しばらく沈黙が続いたが、私は一言だけ答えて通りに走っていった。
「じゃあ行くよ」
すると彼女は、軽く頷いて、離れた私の方をほんの一瞬だけ見送って、それから書店の中へぶらりと歩いて消えていった。私もまた、街の廃れた小径のどこかを、かすれた靴音をたてながら消えた。
〈了〉
(1997.05.11)