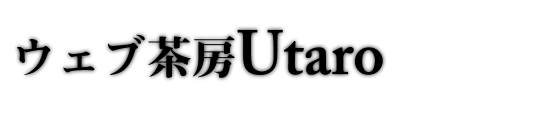![]()
〈一〉出発
1999年9月11日。
朝4時に起床。西武池袋線経由で新所沢駅に到着。私はボランティア活動をするためにここにやってきたのだ。
予定の集合時間より1時間早く着いてしまったので、駅前のファースト・フードへ駆け込み、時間を潰した。そしてさらに時間を潰すべく、東口界隈を散歩し、路地を散策。この界隈は古めかしい商店が一件もなく、パチンコ屋、スナック、キャバレーなどの風俗店が立ち並んでいるだけであった。無論、朝はどこも閉まっていて閑静である。
集合時間15分前を見計らって駅に戻り、同じ参加者が集ってくるのをひたすら待ち続けた。やがて、駅の出入り口付近では、荷物を抱えたある一人の男性が立ち止まった。実を言うと、その人物こそ、今回のボランティアのリーダーだったのだが、どうも似つかわしくない恰好だと勝手に解釈し、彼の存在を除外して、参加者が集まるのを待ってしまったのだった。
すると今度は、前方に8人程度の中学生らが、話をしながらやってきた。彼らは皆ジャージ姿である。引率の先生もいる。一切躊躇せず、その先生が、先程の男性に話しかけた。
いよいよもって不可解さが私の頭をよぎった。まるで体育部遠征の集団に見え、この時点で私は、その後の数時間に及ぶ、彼らとの交流をまったく予期していなかったのである。
ちらりと中学生達がこちらを見た。私はギョッとした。彼らはたった一人佇んでいる私の存在が、どうも気になったのだろう。何だか落ち着かなくなった私は、知らぬ顔をしてさらに待ち続けるしかなかった。
時計を見ると、集合時間の9時半を過ぎていた。ちょうどその頃、駅の構内から若い女性が降りてきた。彼女は、面識のある面持ちで最初の男性に話しかけた。
私はさらに輪をかけて混乱した。最初に来た男性と中学生らが、同じ目的を持った集団であって、そこにもう一人、若い女性が加わった。もう彼らがボランティアのメンバーだろうということは推理できたのだが、いかんせん私の頭の中では、彼らがそのメンバーであるという確証がないことに困惑していて、彼らに直接、尋ねてみることができなかったのである。しかも、一番最初に来ていた私が、一番最後に合流するのは展開的に滑稽であり、まったくもって格好悪い。
そうこうしているうちに、男性と中学生らがバスに乗り込んだ。
ますます、展開的には私にとって、混沌とした状況になった。私はこのまま、知らぬ振りをして帰ろうかと本当に悩んだ。彼ら全員がバスに乗り込んでしまえば、この場から去れる。わざわざ朝早く来たのは無駄足に終わるわけだが、それも仕方がない。ボランティアはとりあえず諦めよう。そう決断し始めた時、さらにこの場の状況が泥水化した。
たった一人、バスに乗り込まなかったその若い女性は、入り口の柱にもたれ込み、誰かが来るのをひたすら待ち続けるかのごとく体勢に入った。従って、バスは依然として発車しない。
私は動こうにも動けぬ状況になった。自分の体が熱くなっていくのが分かった。集合時間はとうに過ぎ、目の前で展開した一集団が、誰かを待ち続けている。それが私なのだということを、この時はっきり感じ取ってはいた。しかしやはり、彼らがWVJのボランティアに来たメンバーであるという確証が持てなかった。
とその時、私は彼女が両手に持っている紙袋の“WVJ”という文字を発見したのだった。その時の、ほっとした気持ちと恥ずかしさと言ったらなかった。私は彼女の目の前に行って話しかけ、自分がボランティア登録者であることを告げると、彼女も〈ああ、間に合った〉といった表情を見せ、小走りでバスに駆け込んだ。
それから車内に座っていたあの最初の男性に挨拶をし、自分も席に着いた。バスが動きだし、新所沢駅のターミナルを抜け出る頃になると、不思議なことに、先程までの恥ずかしさがいとも簡単に消え、何もせず帰ることにならなくて良かった、という気持ちが込み上げてきたのだった。
バスは郊外へ走っていき、私は自分の心の中が真っ白になっていくのを感じながら、目的地に到着するまでゆらゆらと揺れていた。
〈二〉作業
所沢ニュータウンという停車場で降り、一同は、軽く挨拶を交わした。男性リーダーは不精髭を生やし、やや太り気味の体型であった。キャリアはまだ3ヶ月と聞いた。一方、女性リーダーはキャリア7年で、非常に落ち着いた感のある優しい方であった。
それから中学生たちは、埼玉のS市から来た2年生(?)であるという。どう見ても、受験で眉間に皺を寄せる生徒、といった部類ではない。“親父”と彼ら中学生たちに呼び捨てにされた中年先生は、社会科を教えているそうで、この親しみ深い中年先生に、彼らは半ば脅迫されてやってきたようである。それにしても元気がよく、遊び盛りの中学生といった感じで、先生も日頃彼らに手を焼いている様が、ありありと想像できるのが微笑ましかった。
バス停から3分ほど歩いたところに、今回の作業現場となる“株式会社F工務店関東機材センター”がある。
門をくぐり、奥へ進むと、大きな倉庫が幾つか並んでいた。待合室なる所で、全員の自己紹介などが済まされ、その後、リーダーに作業の説明をしていただいた。
作業は、全国から集められたシャツを、アフリカ・ケニアの途上地域に船便で輸送するための、「選別・整理・集荷」が主である。奥の方には、大きなコンテナが1台置かれており、整理された荷物は、このコンテナに収容される。来月、ケニアに輸送されるという。
作業は炎天下の中で行われた。幸い、私は冷房の効いた待合室で、整理され箱詰めされてきた段ボールの荷物を計り、リストを記載してそれを段ボールに貼り付けるという作業を任され、目下、暑い場所で日干しにされたのは中学生らであった。
宅配で送られたTシャツは山ほどある。1日平均数十箱届くらしい。それらをまず開封し、中のTシャツを選別しなければならない。長袖シャツ、ボタンの付いたもの、ブラウス、袖のないシャツ、染みのひどいものなどを除外していく。そして改めてTシャツをまとめて箱詰めし、何枚入っているかを記載、重さを計ってコンテナに収容。
午前中、冷房の部屋にいながらも、私は汗をダラダラかいてしまった。中学生たちは、機敏に箱詰めの作業を進めていた。次々と箱が待合室に運び込まれ、私が重さを計る。そしてリストをガムテープで貼り、彼らがまたコンテナに運ぶという作業の繰り返し。
嬉しいことに、昼食は弁当が出た。いわゆる“ホカ弁”というやつである。コロッケと豚肉のサラダなどが入っていた。ハラペコになった私は、夢中になって勢いよく頬張った。が、一番最初に平らげてしまったのは、案の定中学生たちであった。おそるべし中学生。私は徐々に、彼らの心身の逞しさの虜になっていった。
午後の作業はさらに加速して、あっという間に箱詰めが済まされた。日差しがやや弱くなったせいもあり、また彼ら自身が若さゆえ丈夫ということもあって、疲労をみせる者はいなかった。
私と彼ら中学生は、初めこそ遠慮して口を利かなかったが、そのうち彼らが私のことを“お兄さん”と呼ぶようになって、空気が和んできた。彼らの中の一人が、
「ここまで来るのに遠くなかったですか?」
と尋ねてきた。私は、池袋経由で来たことを説明し、逆に彼に、「埼玉の方から帰れる電車はないか」と尋ねた。すると、その彼は、
「じゃあ、僕たちが乗ってきた電車がいいと思うんだけど、ちょっと先生に訊いてみます」
と言って、先生を呼び込むのだった。
やがて先生が現れて、埼玉を通る電車の近道路線を紙に書いてくれたのである。確かにそれは東京に出るよりも近そうだった。
「もしよろしかったら、帰りは一緒にどうですか?」
と先生はおっしゃった。何だかとても感激して、「是非に」と答えて、話が落着した。
すべての作業が終わり、全員、コンテナの前で記念写真を撮った。時折涼しい風が吹いて気持ちよかった。この日、参加者は交通費をもらい、弁当までいただいた。ちょっとばかり贅沢ではなかったかと思いきや、そういったことを考えるのをやめた。
支援事業として本部から要請される多くの作業は、広義的には緊急を要するものであり、同時に期間が限定されるものである。無論、商いにならない。商いにならないから、人が寄り付かない。だからこそ“ボランティア”なのだが、この限定された期間に多くの参加者を募るのは、非営利活動団体にとって資金的にも時間的にも非常に手間がかかるはずだ。市民を啓発し、協力を呼び掛け、わずかな手当てで活動を有機的に継続させられる保証は何一つなく、リスクが大きい。ある意味、忍耐のいる仕事であると思った。
…そこに一つの国がある。
その途上地域において住民が、物資が届くのを今か今かと待ち続けている…というような想像を根気よく豊かに抱かねば、慈善団体も市民協力者も、労働資本の自腹を切る気にはならないのではないか。想像を抱かせ、無報酬労働に参加するには、やはり並々ならぬ忍耐と強い信念が必要である。
〈三〉今日の日はさようなら
二人のリーダーに別れを告げ、停留所へと歩いた。
この頃、すっかり中学生らと打ち解け合っていた私は、疲労を忘れていた。考えてみれば、12、3歳離れている。まさかこの歳になって、中学生の仲間ができるとは思ってもみなかった。そこに彼らがいて私がいて、話をしているということが、何てことはない普通のことなのだと思えた。
「よくカラオケとか行くんすか?」
返事に窮した私はついに、彼らに打ち明けてしまった。ジャズの――。その時の彼らの驚嘆ぶりは、まるでスターを間近で見ているかのようであった。こちらの予想を遥かに上回るもので、私は途端に恥ずかしくなって、うつむいてトボトボと彼らの後を付いていった。
停留所に着くと、バス賃の細かい硬貨がないことに気付いた。ポケットには500円玉しかない。ちょうどその脇に自動販売機があったので、ジュースを買って500円玉をくずすことにした。彼らもまたジュースを買うために販売機に群がった。そこで私が500円玉を入れようとすると、彼らははしゃいで、私にお金を入れさせなかった。
「おごりますよ!」
そこへバスがやってきて、急いでボタンを押してジュースを取り出した私は、みんなと一緒にバスまで疾走していき、大股でバスに乗り込んだのだった。息を切らした我々は、笑顔を浮かべてお互いの顔を見渡した。
言葉は出なかった。
バスは大きく車体を揺らしたかと思うと、いつの間にか走り出していた。――彼らは私にジュースを奢ってくれた。何ということだろう。彼らの優しさ、私への興味。互いが何か垣根を越えて心を交わしているように思えた。それは言わば、私にしてみれば神様からのジュースであった。ゆさゆさと揺さぶられながら、そのジュースを固く握り締めるしか他なかった。
帰途、彼らと同伴である。しかも先生が引率して詳しい路線を案内してくれた。その小さな旅路は、幾許か続いた。新所沢駅から西武新宿線で所沢まで行き、西武池袋線に乗り換える。一つ先の秋津駅にたどり着くと、JR武蔵野線の新秋津駅に乗り換えるため、駅の外へ出るのだった。
そこは東京下町に似た、老舗の並ぶ駅前商店街であった。町の外れに秋津神社というのがあるようだが、古い言い方をすれば門前町である。夕暮れ時を歩いたせいもあって、なかなか落ち着いた風情がある。どことなく魚屋の匂いが立ち込め、買い物客の雑多なところが周囲を活気づけてもいた。彼ら中学生とこの門前町の秋津の風景が見事に重なり、人間の営みの心地好さがじわりと記憶に残った。
しばし商店街を抜けたら、JR武蔵野線の新秋津駅にぶち当たった。この駅に入る前、私は言った。
「誰か一人住所と名前教えて。そしたらCD送ってあげるよ」
中学生に奢られて、このまま何もせず帰るわけにはいかないと思った私は、お礼にそう約束した。彼らは前にも増して驚嘆した。彼らの喜び様を見ていると、自分が励まされているかのような気持ちになり、温かく、そして血の通った人の心の素晴らしさを噛み締めなければならないと感じた。彼らは私の心を揺さぶり、何気ない言葉と行動で助けてくれたのである。
つまり私は、この日救われたのだった。彼らという仲間が出来、そんな生きた仲間に何かがしたいと思うことは、しごく当然の成り行きであった。駅のプラットホームで一人の男の子が鞄から紙を取り出し、ペンで住所を書き始めた。やがて電車がやってきて乗り込めば、またペンを走らせた。名前の上にはしっかりとした字で、ふりがなが振られていた。
〈埼玉県S市M町 …………〉
それは私と彼らが線で結ばれた瞬間であった。小さなボランティアが、大きな出会いを生んだのである。人間にとって、これほど幸福な1日はないのではないか。
先生は私にお礼を言ってくれた。
「そんな紙、帰ったら破ってゴミにでも捨ててくださいよ!」
電車は進み、南浦和駅に到着した。ここから私は京浜東北線で浦和に出る。彼らはさらに進んで、南越谷に出、付近の新越谷駅から東武伊勢崎線に乗り継ぎ、上ってS駅まで行くのだろう。そこで解散か、夕食を平らげに町をさまようのか。いずれにしても私と彼らとの最後の言葉を交わしたのは、南浦和であった。
私は名残惜しいという気持ちでいっぱいになった。すなわち、もう少し彼らと居たいという気持ちであった。もし何もなく、あのまま新所沢駅で彼らと別れていたらどうであったろう。それはそれで小さな出会いの思い出にはなっただろうが、言ってみれば、お互いにもう会えないという終止符が付いたはずだ。
人間の織り成すドラマは、必ずしも同じ結末になるとは限らない。多くの枝分かれした道を発見し、そこを歩いてみる。何かを発見できるまでとことん歩いてみる。困惑する己の心に、風穴を開けてくれた出会い。半日足らずの出会いではあったが、疲れ果て萎縮した私を、彼らは勤勉に介護してくれ、そして乾き切った口に水を注ぎ込んでくれた。
〈ただ独り、前へ向かって歩けばいい。自信を持とう〉
そんなふうに、あの中学生達が耳元で囁いたような気がした。私は私であるということ、何かを通じて語り合う空間が多く顕在すること。人の心は大きく、無限に広がっているということ――。それは、ボランティアがどうであるという学習結果の問題ではなかった。肌に残った思いやりの暖かさ、そういったものを体験的に感じ取ったのである。
〈了〉
(1999.09)