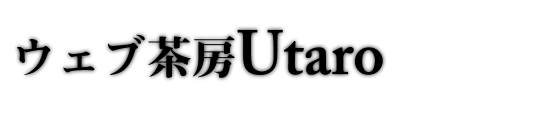![]()
Tとは同じ誕生日であったせいか、何か不思議な縁を感じないわけにはいかなかった。中学校での出席番号は、私が一番で彼が二番。後ろの席にはTがいた。つまりTはずっと私の背中を見ていたことになる。そうしていつの間にか私は、彼を親友として慕うようになった。
とはいえ、そうした状況は一瞬にして過ぎ去ってしまった。一緒のクラスでいられたのはたった1年のことで、それまでは兄弟のような感覚でいられたけれど、それからの2年間は、とても深々とした関係とは言えなかった。互いに気を遣わず、言葉少なげでありながら、どこか距離を置かなければならぬ緊迫した空気を感じたこともたびたびあった。代え難い友とは、彼のことを言うのだろう。私が困り果てていた場に、彼が助っ人として登場した些事がいくつかあったと思う。まるで私を守っているかのようで、その感覚はやはり、近親者のそれと合致していた。
Tとは卒業を機に別れて、音信不通になってしまったのだが、それから10年経ったある日のこと。私は偶然、彼の実家の前の道を通ったのである。するとその家の庭には、黒い花輪が並んでいた。まったく葬式の風景であった。私は身が縮まる思いでそこを通り過ぎた。
あれは何だったのか。
通り過ぎた後、繰り返し繰り返し自分に問うた。誰が死んだのか、という謎がそのうち頭に浮かんできた。
誰が死んだのかはわからないにせよ、あの家で葬式が行われているということは、Tの身内が死んだのに決まっている。だが万一ということを考えても、私はTの身に何かがあったとは思いたくはなかった。
結局、それを調べる勇気は起きなかった。もし肉親が死んでTが憂いでいるとしても、10年近く会っていない彼と直接顔を合わせることは難しいと思ったからである。その難しいと思う理由は、一体何処から来るのか。よくわからない。よくわからないが、少なくとも今は、彼の家族やら友人らが、Tを献身的に支えているに違いないという利己的な結論に行き着いたのだった。
そんなことがあってから月日が経ち、何度もTのことを考えるのだが、会おうという欲求はまったく湧き起こらなかった。いや、会いたいとは心の底で思っている。しかし会いたいというのと、会おうという能動的な意思との差は、厳然とあるのである。
本当の真実が向こうからやってくる時、その時まで、心の中に眠っているTの優しいまなざしを、大事にそのままにしておこうではないか。私の窮屈な結論はこうであった。
Tよ、頼む。生きていてくれ。
いつかきっと会うことができるだろう。
君に話したいことが山ほどあるんだ。10年の空白、いや数十年の空白であっても構わない。その長い年月の重苦しさを、君に語りかけてみたいんだ。それは、兄弟として当然の運命なんだよ。
〈了〉
(1997-2000)