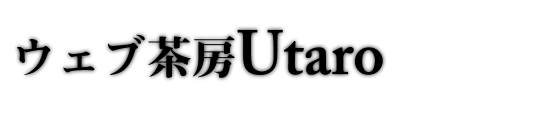![]()
それは、ある冬の日の夜の、至極ありふれた出来事だった。
本屋を出ると、後方からバイクに乗った一人の青年が、突然私に話しかけてきた。
「あのう、すいません。教習所へはどう行ったらいいんですか?」
エンジンの音がやや弱く感じられた。青年は、黒のヘルメットをかぶっており、顔はよくわからなかったが、その青年の肉声と、震えたエンジンの音のみは、何故かしばらく忘れることができないでいた。
「この道をまっすぐ進んで、セブンイレブンの脇の細い道を右に曲がると、そこが教習所です」
「そうですか。ありがとうございます」
「行けばすぐわかると思いますよ」
バイクは、ものすごいスピードを上げて去っていった。私はその反対方向へ歩いていった。
確かに、私の受け答えは日本語であった。その流暢な口語の羅列は、まさに脚本にあるかのような、無駄のない日本語のまとまりがあった。私は歩く途中、心の中でそのことを少し満足げに思い続けていた。
しかし、後になって考えてみると、その受け答えではあまりにもまとまりすぎていて、果たして本当に彼が目的地にたどり着けたかどうかは、疑問の余地が残った。大体、まっすぐ行ったとしても、コンビニエンスストアまでの距離はかなりあり、途中で違う道を右折したりして、かえって道に迷うのではないか、と。はっきりと、そこまで「距離がある」ことを告げればよかったと後悔した。
しかも厳密に言えば、細い道を右に曲がるのではなく、「右に曲がる細い道がある」という表現が正しい。
何とも粗末な道案内ではなかったか。
だが、それ以上複雑に考えるのはよそうと思った。なんだか馬鹿馬鹿しくなってきたのだ。それよりも、日常的で、それもごくごく短い会話に遭遇した自分の新鮮な気持ち、その初々しさに出合えたことを思った方がいい。それは本当に久しぶりに出合えた生きた情景だったのだから。
そう、些細なことではあるが、ありのままの日常に触れることで、自分が瑞々しさを取り戻し、息を吹き返したような気持ちを味わえたことを大事にしたいと思った。青年はどこから現れ、何をしにそこへ行くのか。想像は膨らむ。
〈了〉
(1997-1988)