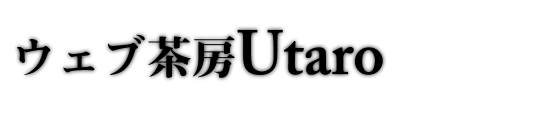![]()
以下のエッセイは、1995年10月9日東京ドームで開催された、新日本プロレス『激突!!新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争』のTV観戦記である。某プロレス雑誌の読者投稿文として、1995年当時に掲載された。
プロレス界にとってドームというのは特別な空間であり、野球のグラウンドとしての意味合いとはまったく異なる。10.9東京ドーム。そこに6万7千人の観衆を集めたということは、多くのプロレスファンがこの対抗戦をいかに待ち望んでいたか、それを顕著に示した証明だといえる。
プロレス界は、半ばUの幻想が真に幻想であることを知りつつも、それを黙認した形で野放しにしてきた。プロレス=真剣勝負ではないという言われ方には過剰なまでに反論を続けたが、それを現実に証明させる場所がなかったために、プロレス否定論を打ち消すことができなかったのだ。
どちらが場所を与えなかったのかは問題ではない。プロレス界に長い間フラストレーションがたまっていたことが重要なのだ。今回の10.9ドームで、とてつもなく大きく膨れ上がったフラストレーションが一気に爆発した感じがする。誰もが、はっきりと目に見えるものを求めていた。現実に新日本の選手とUインターの選手が相対したとき、マグマとマグマのぶつかり合いのように思えた。これは明らかに反作用的なぶつかり合いである。負と負のぶつかり合い、陰と陰のぶつかり合い…。かつて、これほど壮大な対立構造を生んだイデオロギーは、プロレス界には存在しなかった。
何故、新日本プロレスとUWFインターが闘わなければならなかったのか。それは「プロレス対U」という、宿命とも言うべきつぶし合いの論理がそこにあったからだ。改めて書く必要はないと思うが、Uは新日本の中から生まれ、そして離散して育っていった。しかしそれはあくまでも新日本の体系から外れた遺伝分子であって、お互いに認め合った関係ではなかった。そうしてUがプロレスを否定した瞬間から、対立構造として深い溝ができてしまったのである。
その昔、“真剣勝負”という言葉に躍らされていた時代があった。もちろんそれを持ち出したのはUである。どういった意味でそれを使ったのかは分からないが、とにかく、プロレスを否定しなければUの存在はありえなかった。それは限りなく真実に近いことである。Uが光り輝くためには、プロレスを持ち出して、それを打ち砕くしかなかった。
Uインターは現実にプロレスを使ってUの誇大化を画策する。Uインターのリングにベイダーやハシミコフを呼び入れ、彼らからプロレスの吸引力を奪っていき、Uの幻想を肥大させる。その象徴として、
「プロレスリング世界ヘビー級」
というベルトを利用した。
だが、Uは新日本を打ち砕けなかった。打ち砕けないどころか逆にプロレスに飲まれてしまった。そう、新日本にではなくプロレスに飲まれてしまったのだ。武藤対高田戦では、Uを崇める者にとって屈辱以外なにものでもない、“足四の字固め”で負けるという大失態を演じてしまう。その時点でUが啓蒙していたサブミッションの価値は、足四の字固めと同等になった。そこにはもう、かつての栄光であるとか、「Uスタイルが最強である」といったまやかしなどない。プロレスの逆襲によってUの幻想は崩壊したのである。
ここで言えるのは、10.9ドームは、プロレス界に、いや格闘技界にさえとんでもない結論を出してしまったということ。この結論を踏まえると、Uというのはプロレスの外にあるのではなく、むしろ全レスラーの内にある観念を指していることに気づく。どんなレスラーにも観念上、Uは存在するのだ。しかしその観念は絶対的なものではなく、いくつかのスタイルの一つにしかすぎない。臨機応変にいくつかのスタイルを使い分けるのが、プロレスラーの本質であったにもかかわらず、U戦士は一つの観念に固執してしまったのである。それが絶対的なものだと、誰が決められよう。
プロレスとは何かを本質的に探っていったとき、そこにUの悲劇があった。別の側面から10.9ドームを見たら、非常に欝屈したものが見えてきた。それを知って初めて、長州が何を言いたかったのかが理解できたのである。
〈了〉
(1995)