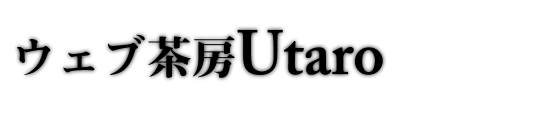![]()
〈一〉
2002年6月2日――。劇団在籍時代、親しかった友人の一人に、サクちゃんという男がいた。それはよく飲みに行ったり、あるいはどちらかの家に寝泊まりしたこともあった。そんな彼とは、4年前の1998年の秋に会って以来、すっかり音信不通となってしまったのである。
私にとってサクちゃんとは、「良き後輩、良き親友」といった関係だった。こちらが何か用があって電話をすれば、彼は一目散にすっ飛んで来てくれる。駅にいると告げれば、駅まで迎えに来てくれたこともしばしばあった。とにかく、こんな親切な友人はいないと私は感じていた。
だが、それは少々、私の思い違いの部分もあったのではないかと、最近になってじわりじわりと頭を巡るのだ。「良き後輩、良き親友」というのはあくまでも私の主観であって、実際当人は私に対してさほど関心はなく、あのすっ飛んで来てくれるというのも、実は単なる彼の性格的な行動性だったのではないかと思うのだ。
思い違いの確たる証として、私が劇団を脱退した直後から、その関係は薄まっていく。劇団の稽古場を通じて接触してきたそれまでのつながりは、あくまで彼と劇団とのつながりであり、私個人との直接的なつながりではなかったのである。それ自体がなくなって出会う必然がなくなる――悲しいかな、私はそれにまったく気づかなかった。
結局、あの頃を振り返ってみると、彼との付き合いがいったい何だったのかよくわからない。自分自身の忘れ去りたい過去の一群に混じって、彼との交際のすべてがそこにあり、私はその支離滅裂なる恣意の整理場所を見つけることができない。
ただ一つだけ言えるのは、現在までつなぎ止めている彼へのささやかな眼差しを、偽りのない感謝の念と彼の前途を祝福する気持ちとに振り替え、あやふやな時代の思い出として記憶にとどめておきたいということである。
〈二〉
2004年4月15日――。サクちゃんの夢を見る。
これまで何度となく見てきたサクちゃんの夢は、いつも簡単に会い、簡単に去っていった。つまり非常に抽象的であった。
しかし昨日見た彼の夢は、実に具体的というか実在感のある肉の存在である。彼は私に対して細かく文句を言いつつ、それとなく手助けをしてくれる。言葉とは裏腹にちらちらと見え隠れする、彼の優しさがよく表れていた。
そうあってほしいという私の願望であるのだろうが、やはりどこか空しい、絶句する一歩手前の、虚無感を感じないわけにはいかない。時代が経過し、人とのつながりも変化する。彼と共に過ごした時代の背景は、今の時代にはそぐわないまったく別の背景であって、この今の時代を、昔と同様に彼に寄り添って生きることは、到底考えられないし、あり得ないことだ。
〈三〉
2004年6月10日――。サクちゃんの夢を見る。
シチュエーションは学校の教室。彼がなにやらしつこく私に言葉で迫ってくる。あまりにもしつこいので、私は彼を引き離そうと、彼の顔面を足で踏みつぶした。彼は一瞬、驚いた表情を見せるのだが、ひるむまもなく、また私に肉薄してくる。
そのうち今度は、私の座る椅子の下に潜り込み、彼の頭上に位置する机の上へ、両手を差し出してきた。そしてその両手は、必死に私の掌を探しているようだった。
万感込み上げてくる。私の心の中で、何かが瓦解したような気がした。
…そこで夢から覚める。しかし私は、その夢の余韻もあって、さらに想像して自分なりに結末を付け加えた。つまりこうである。
掌を探し求める彼の腕を掴み、そして彼の身体を抱き上げると、私は彼を教室の外へ素早く連れ出した。誰もいないその廊下で、私は泣きながら彼を抱擁する。私の魂から直接こみ上げてきた、なけなしの愛情表現である。
たとえ夢とはいえ、サクちゃんに対して、顔面を踏むという行為は、自分自身驚きとショックを隠せない。その激しい感情の起伏の裏には、私自身でさえよくわからない、複雑な思いがあるのだろう。そこには、彼があまりにも遠くへ行ってしまったことへの、憎悪があるのだろうか。
だがいずれにせよ、私は今、彼にどうすることもできない。彼に対する言葉も見つからないし、ただただ、ありのままの現実を行くだけである。それでも、一つだけ言えるのは、私の生涯を通じて、彼の幻影が、心の中で完全に消えることはないということである。
〈四〉
2006年3月22日――。サクちゃんの夢を見る。
久しぶりに彼と再会し、私の自宅に招き入れる。
が、私の彼女とサクちゃんが遭遇してしまい、彼は目を真っ赤にして、
「バカ!」
と言って去っていってしまう。
私と彼女はその住処を離れることにし、翌日、仲間と別れのパーティが開かれる。サクちゃんもその中にいたが、彼とは何のわだかまりもなく、からっとさわやかに別れを告げた。夢から覚める。
昔、よくサクちゃんの家に行って泊まった。
彼の部屋には、私が進呈したタイガーマスクのマスクが棚に飾ってあり、それがそこにあるということだけで、私自身、なんだか随分と安堵感を得ていた気がする。彼と幾分でも繋がっているという意味で――。
まったく会わなくなってからのことだが、二度三度、彼の家の前まで足を運んだことがあった。もし、あの二階の寝室の明かりが灯っていたら、そこにサクちゃんがいるのだ、と分かる。
そういうつまらぬ期待を得ようと、実際、胸を高鳴らせて足を運んだものの、部屋の明かりが灯っていることは決してなかった。
そうして私は、彼のことを心底忘れるよう徹した。
もう彼は私と繋がっていないのだという現実を咀嚼する。
それは、胸の奥からこみ上げてくる諦念であったし、一つの関係性に対する深い絶望感であった。私はその諦念やら絶望やらに屈服せず、小さな情緒にとどまることをきっぱりやめたのだった。
それでも、やっぱりサクちゃんの夢を見る。彼は、突然私のところにやってきて挨拶をする。今は、富山にいる、というのだ。
ただそれだけを私に告げて、彼は去った。いや、去ったというよりも、消えた。
夢から覚めると、何かその富山にいるということが、ひどく現実のような気がした。彼を思い返すことはなくとも、夢の中に彼が現れ、また一つ新しい現実を生み出す。まるで人伝の噂のように、現在の彼の居場所を教えてくれるように思えた。
だがサクちゃんは、もうこの世にいないのではないか。
そういう根拠のない別の現実感も、あるにはあった。どこか遠くにいるという現実、彼はとっくに死んでしまっているという現実。二つの相反する現実が、私の心の中で、何故かうまい具合に融和されて、サクちゃんという人間の所在が不確定ながらも、地べたに土着しつつあるのだ。彼と私の古い関係において、それ以上の現実はあり得ないのだから。
再び彼の夢を見る。
これまた再会の夢だ。ごく自然に、何気なく再会し、場面展開と共にどこかへ消えていく。
久しぶりに逢ったときの一瞬の新鮮さはあっても、それは長く続かない。すなわち、小学生時代の同級生の夢を見るような感覚と同じである。
記憶の奥に断片化された彼が夢となって現れるのであろうが、どう正直に自己意識をとらえようとしても、彼と会いたい、再会したいという積極的な気持ちは、現実には湧いてこない。ただぼんやりとした影、霧のようにかたちにならない影だけが、記憶に残存しているようだ。
それはむしろ小説化された存在であろう。
〈五〉
2007年11月14日――。サクちゃんの夢を見る。ほとんど狂気の沙汰で、憎しみの渦巻く殺意の成れの果てといったところ。まったく訳がわからない。これもすべて風邪をひいて体調が万全ではないからだろう。自分の経験した現実世界と空想、そして創作の新しいアイデアとがまぜこぜになってしまい、夢が何かの暗喩である、とフロイトが示唆するような結果にならない。これをそのまま鵜呑みにしていたら、自己崩壊につながる。私にとって夢の中とは、数巻のラッシュプリントを延々見るようなものである。
〈六〉
2008年11月13日――。サクちゃんの夢を見る。だらだらと寛ぎ、だらだらと付き合う。そこには至福の時があった。ただ寝転んで、他愛のない話をしているだけでも、この人間にだけは遠慮はいらない、着飾らない、抱きしめてあげられるという類のものである。
そう言えば、今月末にいよいよあの「K公会堂」が解体されてるという記事を、広報で読んだ。あの当時でも老朽化が甚だしく、使いづらかった面があったが、私にとっての時代のシンボリックな建築物が無くなるとなると、その前に写真に収めておこうという気にもなる。少なくとも今、どんな状態なのであろうか。
〈七〉
2010年7月28日――。サクちゃんへ
たいへんお久しぶりです。お元気でしたか。お変わりありませんか。
最後にあった日から数えると、かれこれ10年が経ちました。こちらも日々元気に変わりなく暮らしています。あの頃のことを忘れたことはなく、何かの折に思い出すこともしばしばありますが、10年という歳月の流れは途方もなく速かったように思います。
お互い、10年で様々な変化や様々な節目を迎えたことでしょう。もし、また再会することがあるのなら、ということを、常々考えていました。また新たな門出の中で、気兼ねなく再び交遊できるのなら、それが私の最高の望みです。
懐かしい話でもしながら、ゆっくりとのんびり二人で旅行でもしてみたいものです。
ご返信いただければ幸いです。
〈八〉
2011年12月12日――。サクちゃんの記憶を捨てていく。もはや彼との明解なる再会は、13年という積み重なった時間の重みによって押し潰され実現不能となっている。再会に伝う装置をすべて失ってしまったのである。忘れていくことが、彼への最大の応援歌となるのだ。
そうして捨てていかなくては、いま目の前の親友に対して、親身として全力でぶつかることができない。サクちゃんという存在は、そうした彼らのために犠牲になるべきである。彼の墓標が今、私の心の隅に出来上がった。
〈了〉
(2011.12.15)