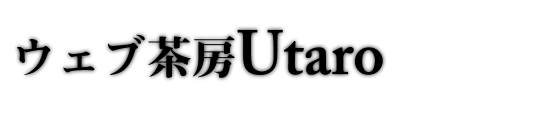![]()
疎外されることば
ある意味において、教科書全般に言えることかもしれないが、その最初の入口が取っ付きにくいものになっている。少なくとも私の10代においては、「教科書」というものをそういうふうにとらえ、よほど必要とならなければそれをなかなか開かなかった。従って勉学が滞りがちになり、一夜漬けの片付け仕事的な場合が多かった。 唯一、この筑摩書房の国語教科書だけは、比較的例外であった。皮肉にも取っ付きにくさでは群を抜いているように思われ、まったくの大人目線による装幀と構成になっていた。教科書の格調の高さというのは、しばし勉学の本質の妨げになるが、私自身が国語学習の中身をどう解釈し会得したかにかかわらず、一つの文学書物として、私は不思議とこの国語教科書から惑溺するものを感じたのだ。
唯一、この筑摩書房の国語教科書だけは、比較的例外であった。皮肉にも取っ付きにくさでは群を抜いているように思われ、まったくの大人目線による装幀と構成になっていた。教科書の格調の高さというのは、しばし勉学の本質の妨げになるが、私自身が国語学習の中身をどう解釈し会得したかにかかわらず、一つの文学書物として、私は不思議とこの国語教科書から惑溺するものを感じたのだ。
唐木順三という評論家についてはまったく知らなかった。1990年の高校生の、一般的な嗜みからして、唐木順三という人との接点を結びつけるものが、私自身には何一つなかった。
故に、いきなり唐木順三著の「疎外されることば」は、強烈な印象を伴う鎮静剤となった。
それまで馴染み深かったいわゆる児童文学の平穏牧歌的な境界線を踏み越え、“ことば”が“疎外される”という主題に出合ったとき、新たな批評文学という分野に踏み入れる武者震いを覚えた。
《ところで、その疑念も、絶望も、一般的にいえば思惟そのものも、実はまたことばを媒介にして行われていることに気づく。我々の迷いも、疑いも、心の中で、発音しないことばによって運転されている。ことばの一般法則、ことばの一般的方法を離れては、ことば自身をも疑うことができないことを自覚するとき、一刀両断、ことばをことば以外の力、意力をもって否定せざるをえなくなる。そして我々はことばの発達しない原始段階に帰って、ああ、とか、おお、とか、やあ、うん、かッ、というようなさけびへもどる。絶言栓、不立文字の原始経験へ帰る。そしてこのもどり、帰ったところが、真実のことば、美しいことばの誕生する場所であろう。文学、なかんずく詩はそこから起こった。そして今日のだれかれでも、真におのが実存的な体験を、実存的に語ろうとするとき、おのずからに瞬間的に詩人である》
この頃私は夏目漱石の文庫本を揃え始め、文学と小説の醍醐味を知った。よりいっそう教科書を読み込めば、唐木順三と筑摩書房の精神について触れることができたかもしれないが、無論、そのような練達した度量を持ち得ていない。漠然と「疎外されることば」を読み、漠然とその時分の自然な流れとして、漱石を読み始めたに過ぎない。
結果としてその宿題は、今こうして再び教科書を開くとき、装幀、文体、文脈、そして作家らの思考の旅となって託された。単に郷愁として読み返すのではなく、教科書の意図を超え、まさに文学への旅の地図としての一冊に塗り変わったのだ。言うまでもなくそれは、唐木順三の「疎外されることば」から始まった。